

目次
子どもの「おちんちんの皮(包皮)」がむけない…これって大丈夫?と心配される保護者の方はとても多いです。
実は、幼い男の子の包茎はほとんどが自然なもので、あわてて治療する必要はありません。
「いつかむけるようになるのだろうか」「何か特別なケアが必要なのだろうか」といった疑問は、ごく自然なものです。
当クリニックでも、「包茎って治療が必要なんですか?」というご相談は、日常的によくいただきます。
この記事では、小児外科医としての視点から、子どもの包茎ケアに関する基本的な考え方と、当クリニックが大切にしている「焦らず、段階的に進めるケア方針」について、ご紹介します。
生まれたばかりの男の子の赤ちゃんや、幼いお子様では、亀頭(おちんちんの先端部分)が包皮で覆われ、完全に露出しない状態(包茎)が一般的です。
これは「生理的包茎」と呼ばれ、多くの場合、病的なものではありません。亀頭と包皮の内側の皮膚が、成長過程で一時的に癒着(くっついている)している状態なのです。
この癒着は、お子様の体の成長に伴って、亀頭が大きくなったり、男性ホルモンの影響を受けたりする中で、自然に少しずつ剥がれていきます。
そして、多くは幼児期後半から学童期、思春期にかけて、包皮がスムーズに翻転(むけること)できるようになります。
したがって、「包皮がむけない」というだけで、直ちに医学的な問題があるわけではありません。
まずは、お子様の自然な発達を見守ることが、基本的な姿勢となります。(詳しくは、当クリニックのウェブサイト記事「おちんちんの皮がむけない(包茎)」もご参照ください。)
ただし、すべてが経過観察のみで良いわけではありません。
以下のような状況が認められる、あるいは繰り返される場合には、衛生面や排尿機能への影響を考慮し、医学的な介入(ケアや治療)を検討する必要があります。
おしっこをする際に、包皮の先端が著しく膨らむ(バルーニング現象)、尿線が一定せず飛び散る、排尿に時間がかかる、痛みを訴えるなど。
亀頭や包皮が赤く腫れたり、痛みが出たり、膿(うみ)が出たりする「亀頭包皮炎」を頻繁に繰り返す場合。
癒着が非常に強い、あるいは成長しても全く改善傾向が見られない場合で、医師が介入を必要と判断した場合。
当クリニックでは、無理な処置を避け、お子様の心と体への負担を最小限に抑えることを大切にしています。
そのため、以下のように2つのステップに分けて段階的にケアを進めています。
– 包皮をやさしく引き下げたときに、おしっこの出口が見えればOK。先端1/3程度の翻転が目安です。
– これが達成されると、バルーニングや炎症のリスクが大きく減少します。
– ステップ1を達成していれば、残りの癒着は思春期に自然に剥がれることが多いため、無理に進める必要はありません。
– 無理な翻転は「嵌頓包茎(かんとんほうけい)」の原因になることもあるため、注意が必要です。
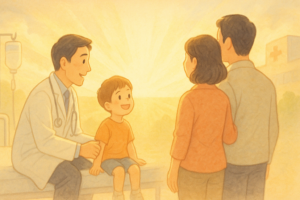
医師の指導のもと、ご家庭で行っていただくケア(包皮翻転指導を含む)は、主に以下の通りです。
皮膚が柔らかくなっている入浴時に、痛みのない範囲で、ゆっくりと包皮を引き下げる練習です。(目標はまずステップ1です)
– 包皮先端の皮膚を柔らかくし、伸展性を高める効果が期待できる塗り薬です。炎症を抑える目的でも用いられます。
ご家庭でケアを行う際に、絶対に留意していただきたいのが「嵌頓包茎」の予防です。
– 包皮を翻転させた(引き下げた)後は、必ず元の位置に戻してください。
– もし、引き下げた包皮が亀頭を締め付けたまま戻らなくなると、亀頭がうっ血して腫れ上がり、激しい痛みを伴う「嵌頓包茎」という状態になります。これは緊急の処置が必要な状態ですので、万が一発生した場合は、直ちに医療機関を受診してください。
また、無理な力での翻転は絶対に避けてください。裂傷や瘢痕形成のリスクがあります。
「手術は必要ないの?」というご質問もよくお受けします。包茎に対する手術は、限定的な場合にのみ検討されるべきものと考えています。
– 主な手術対象は、繰り返す亀頭包皮炎の結果、包皮の出口(包皮口)が硬く、瘢痕(きずあと)になって狭くなってしまった「瘢痕性狭窄(はんこんせいきょうさく)」の症例です。この状態では、軟膏や用手的なケアでの改善が難しい場合があります。
– 一方、単に包皮口が狭いだけで瘢痕化していない場合は、まずは思春期頃まで経過を見ることが多いです。
– 思春期を過ぎても亀頭が全く露出せず、狭くなっている部分(狭窄帯)が長く、かつご本人が整容面や機能面で困っており、手術を強く希望される場合に、初めて手術が選択肢として検討されます。
ほとんどの生理的包茎や、軽度の機能的問題を伴う包茎では、手術に至ることはありません。
ステップ1が達成された後も、再癒着を防ぐために、入浴時などに定期的に包皮を翻転させて清潔を保つことが大切です。
ご家族の中で時々チェックすることが習慣化され、最終的に、お子様が自分でできる習慣が確立するまでフォローさせていただき、大丈夫となれば卒業します。包皮のケアと時々の自己チェックが習慣化し、安定したら、治療を終了します。
もちろん包皮のチェックを忘れてしまい、結果的に元に戻ってしまうようなケースもありますので、ご不安が強い場合や、また包皮が元に戻ってしまったと感じる場合は、その都度受診もしていただきます。
お子様の包茎については、小児泌尿器の間でも、一定のコンセンサスが得られていない領域でもあります。
ですから、当クリニックでは、お子様一人ひとりの状態やペースに合わせた治療の目標と、ケアを、一緒に考え、サポートさせていただきます。
本人の様子、ご家族の意向、不安を考慮して、治療のバランスを考えながら、無理せずに治療を進めることが大切と考えています。
当クリニックでは、バランスを考慮しながら、段階的かつ負担の少ない方法でケアを進めることを基本方針としております。