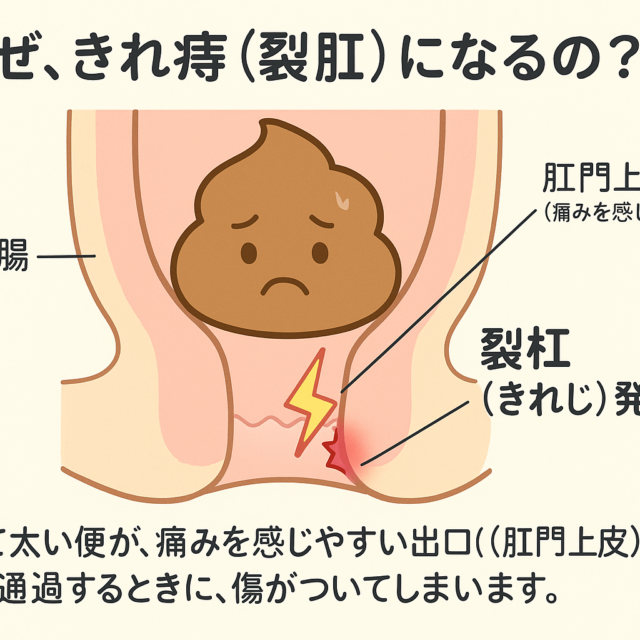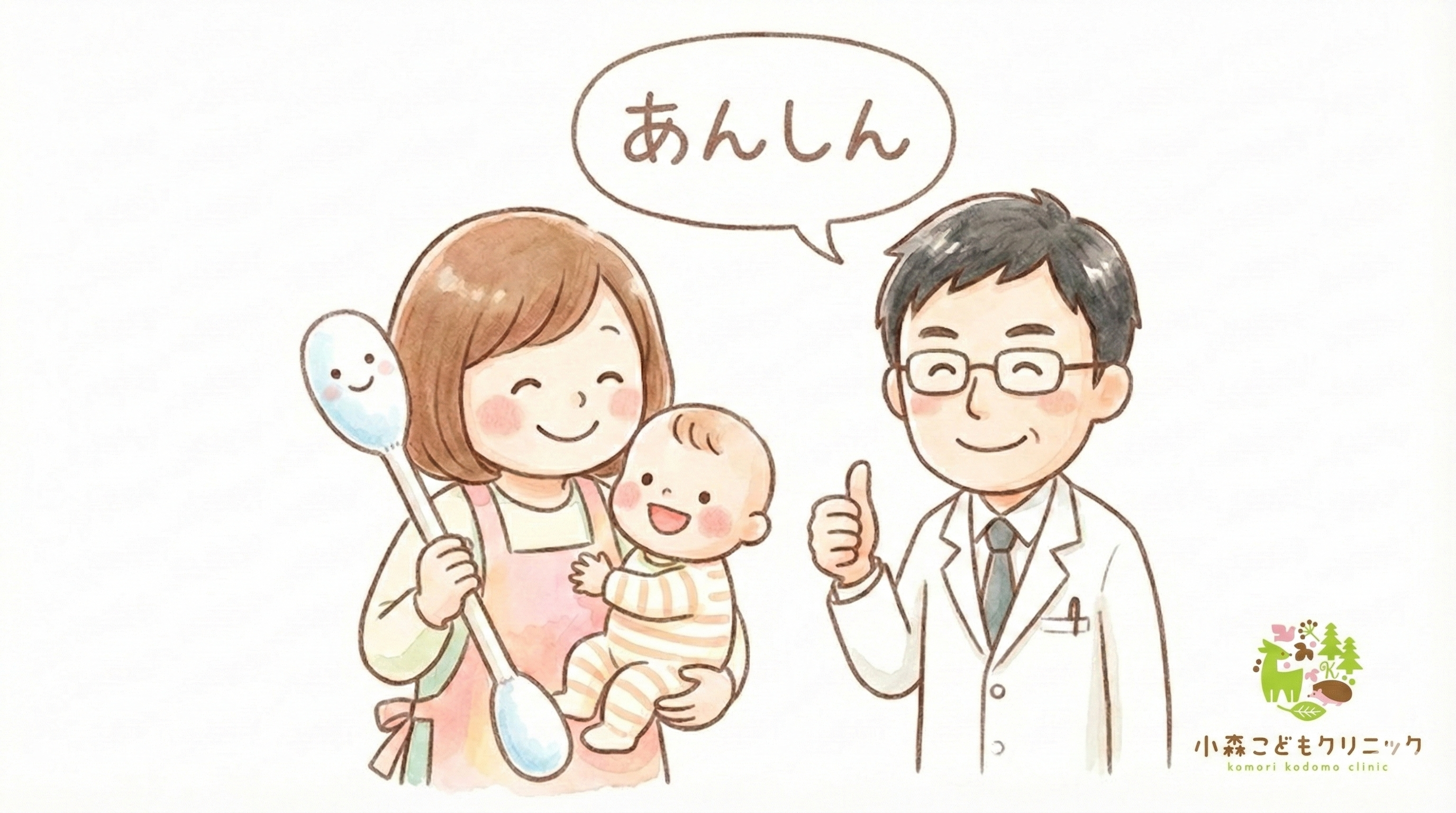目次
はじめに:わが子の“見えない”お腹の痛みと、どう向き合うか
「お母さん、お腹が痛い…」
保育園や学校に行く前になると繰り返される、わが子のつらそうな訴え。病院に連れて行っても「特に異常はありませんね」「ストレスかもしれません」と言われ、整腸剤だけをもらって帰ってくる。そんな経験をされているご家族は、決して少なくありません。
便秘が続いているかと思えば、急に下痢をすることもある。痛みの原因がはっきりしないため、親としてはどう対処すれば良いのか分からず、お子さん自身も「気のせいじゃないのに」と、見えない痛みに一人で苦しんでしまいます。
もし、あなたのお子さんがそのような状況にあるのなら、それは「機能性腹痛症」や「過敏性腸症候群(IBS)」と呼ばれる、腸そのものが非常に“過敏”になっている状態が原因かもしれません。
これは、腸にポリープや潰瘍といった目に見える病気はないのに、機能(働き)に異常が生じ、痛みや不快感、便通の問題を引き起こす状態です。そして、この“過敏さ”の正体こそ、「第二の脳」である腸の神経システムが、些細な刺激に過剰反応してしまう誤作動に他なりません。
この記事では、この“過敏な腸”を落ち着かせ、正常な働きを取り戻すことで、お子さんの腹痛と、その結果として起きる便秘の両方を、根本から解決するための栄養学的アプローチを、具体的にお伝えしていきます。
▼この記事でわかること
✔️お子さんの繰り返す腹痛の「本当の原因」
✔️専門医が考える「過敏な腸」を落ち着かせる3つの柱
✔️今日から家庭で実践できる具体的な食事の工夫
ゴールは、応急処置で済ませるのではなく、根本から腸を健康な状態に育てること。
「またお腹が痛くなるかも」というお子さんの不安を取り除き、ご家族みんなが安心して過ごせる「快適な毎日」を取り戻すこと。そのための、新しい一歩をここから始めましょう。
第1章:“過敏な腸”の正体 – 機能性腹痛症(過敏性腸症候群)とは?
「はじめに」では、お子さんの繰り返す腹痛や便秘の背景に、腸が“過敏”になっている状態がある可能性をお話ししました。この章では、その正体である「機能性腹痛症」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
第1節:機能性腹痛症は「気のせい」ではありません
病院で「異常なし」と言われると、「もしかして、この子の気のせいなのだろうか?」と不安に思われるかもしれません。しかし、それは断じて違います。機能性腹痛症は、お子さんが現実に感じている、本物の痛みです。
では、なぜ検査では「異常なし」なのでしょうか。
それは、この状態が、胃カメラやエコー検査などで発見できるような「器質的な問題(=臓器の形の問題)」ではなく、「機能的な問題(=臓器の働き方の問題)」だからです。
車で例えるなら、エンジンやタイヤの部品(形)はどこも壊れていないのに、電気系統やコンピューター(働き)の調子が悪くて、うまく走れない状態に似ています。お子さんの腸も、見た目は綺麗で健康でも、その働き方や感覚が“過敏”になっているために、つらい症状が引き起こされているのです。
第2節:すべての鍵を握る「腸脳相関」
この「働き方の問題」を理解する上で、最も重要なキーワードが「腸脳相関(ちょうのうそうかん)」です。これは、脳(第一の脳)と腸(第二の脳)が、自律神経などを通じてお互いに密接に情報をやり取りしていることを指します。
この双方向のコミュニケーションが、機能性腹痛症の悪循環を生み出します。
✔️脳 → 腸への影響
学校での緊張や不安、ストレスなどを脳が感じると、その信号が腸に伝わり、腸が異常な動き(けいれんしたり、動きが止まったり)を起こして腹痛や便秘の原因となります。
✔️腸 → 脳への影響
逆に、食事や腸内環境の乱れによって腸が刺激を受けると、その不快な信号が脳に伝わります。すると、脳は不安を感じやすくなったり、痛みをより強く感じやすくなったりします。
この悪循環が続くと、腸の神経はどんどん過敏になり、普通なら気にならないような、食べ物の移動やガスの発生といった些細な刺激に対しても、「痛み」という強い警報を鳴らしてしまうようになるのです。
第3節:症状のタイプ:腹痛+便秘、腹痛+下痢
機能性腹痛症(過敏性腸症候群)は、主な便通の状態によって、いくつかのタイプに分けられます。
✔️便秘型:腹痛と共に、硬い便やコロコロした便が特徴。
✔️下痢型:腹痛と共に、急な便意や軟便・水様便が特徴。
✔️混合型:便秘と下痢を交互に繰り返す。
このように、現れる症状は様々です。しかし、どのタイプであっても、その背景には「過敏になった“第二の脳”」と「乱れた腸脳相関」という共通の問題が隠れています。
ですから、根本的な解決を目指すには、便を出す・止めるといった対症療法だけでなく、腸の過敏さそのものを鎮め、腸と脳のコミュニケーションを正常化してあげることが不可欠です。
次の章では、では一体「なぜ、腸は過敏になってしまうのか?」、その具体的な引き金について探っていきます。
第2章:“過敏な腸”を落ち着かせるための3つの柱
第1章では、お子さんの不調の背景に「過敏な腸」と「腸脳相関の乱れ」があることを解説しました。では、どうすればこの繊細で過敏な状態を落ち着かせ、正常な働きを取り戻すことができるのでしょうか。
私たちは、そのためのアプローチとして、以下の3つの重要な柱があると考えています。これらは、どれか一つだけを行うのではなく、並行して取り組むことで、相乗効果を発揮します。
柱① 腸内細菌を整える – 腸内環境の“土壌改良”
過敏な腸は、しばしば腸内環境、つまり腸内細菌のバランスが乱れています。腸を植物が育つ畑に例えるなら、まずはその“土壌改良”から始めることが不可欠です。
✔️プロバイオティクス(善玉菌を入れる)
これは、畑に良い微生物を直接まくアプローチです。特に私たちが注目しているのが、医療機関でも処方される「ミヤBM」などに含まれる酪酸菌(らくさんきん)です。酪酸菌は、腸の中で「酪酸」という物質を作り出します。この酪酸は、腸の粘膜細胞にとって最高のエネルギー源であり、同時に腸の炎症を抑える強力な働きも持っています。
✔️プレバイオティクス(善玉菌を育てる)
こちらは、畑に肥料を与え、もともといる良い微生物を元気に育てるアプローチです。善玉菌のエサとなる水溶性食物繊維(海藻、きのこ類、根菜など)やオリゴ糖を食事に取り入れ、腸内環境を内側から豊かにしていきます。
柱② 消化機能を高める – “消化酵素”を作る力を養う
どんなに良い栄養を摂っても、それをきちんと分解・吸収する「消化力」がなければ、かえって腸の負担になってしまいます。消化力が弱いと、未消化の食べ物が腸を刺激し、過敏さを助長してしまうのです。この消化力を支えるのが、胃や膵臓で作られる「消化酵素」です。
私たちは、お子さんの体が消化酵素を自力で作れる“工場”としての機能を取り戻すことが重要だと考えています。そして、その工場をフル稼働させるには、以下の栄養素が不可欠です。
✔️工場の「材料」:タンパク質(アミノ酸)
消化酵素という製品そのものは、タンパク質から作られています。質の高いタンパク質が不足していては、そもそも製品を作ることができません。
✔️工場の「働き手」と「設備」:亜鉛、鉄、ビタミンB群
材料があるだけでは、工場は動きません。酵素が作られ、働くために不可欠な亜鉛、鉄、ビタミンB群といったミネラル・ビタミンが、「働き手」や「設備の潤滑油」として必須の役割を果たします。これらの栄養素が、工場の生産性を支えているのです。
柱③ 炎症をコントロールする – 腸内の“火事”を鎮める
過敏な腸の背景には、多くの場合、目には見えないレベルの「微細な炎症」が存在します。この腸内の“火事”を鎮めるアプローチは、根本解決のために極めて重要です。
✔️炎症を抑える栄養素:ビタミンD
ビタミンDは、骨の健康だけでなく、免疫機能を調整し、過剰な炎症反応を抑える“火消し役”としての働きが注目されています。
✔️炎症の“火種”を減らす食事法
1. グルテンとカゼインを控える
小麦製品に含まれるグルテンと、乳製品に含まれるカゼイン。これらは栄養価の高い食品ですが、一部のお子さんにとっては、その構造の複雑さから腸を刺激し、炎症の“火種”となりやすいことが知られています。もし様々な手を尽くしても不調が続く場合、これらを一時的に食事から減らしてみることで、腸が落ち着きを取り戻すことがあります。
2. 食事のローテーション
毎日同じものばかり食べていると、その特定の食材に対して腸の免疫システムが過剰に反応し、炎症(遅延型フードアレルギー)を引き起こしやすくなることがあります。特定の食材に負担をかけすぎないよう、いろいろな種類の食材を日替わりで循環させる(ローテーションする)ことは、腸の炎症をコントロールする上で非常に有効な戦略です。
第3章:【実践編】今日からできる具体的なステップ
第2章で解説した3つの柱を、日常生活でどのように実践していくかを具体的に紹介します。
難しく考える必要はありません。すべてを一度に完璧に行おうとせず、まずはできそうなことから、一つずつ試していくことが成功への鍵です。
ステップ1:食事記録をつけて“火種”を探す
最初におすすめしたいのが、簡単な食事記録をつけることです。これは、カロリー計算などの難しいものではなく、お子さんの体が何に反応しているのかを探るための「観察日記」です。
✔️記録する内容:
「いつ」「何を食べたか」に加えて、「お腹の調子(痛みの有無や程度)」「便の状態」「機嫌や元気さ」などを簡単にメモします。
✔️目的:
記録を数日から1週間ほど続けると、「特定のものを食べた後にお腹を痛がることが多い」「小麦製品が続くと便が硬くなるようだ」といった、食事と症状の隠れたパターンが見えてくることがあります。
この記録は、お子さんの体の「声」を聴くための、何より重要な第一歩です。また、医療機関を受診する際にも、非常に貴重な情報源となります。
ステップ2:食事のローテーションと「GFCF(グルテンフリー・カゼインフリー)」の試し方
食事記録で特定の傾向が見えてきたら、あるいは、何が原因かまだはっきりしない場合でも、次に行うべきは食事による刺激を減らす工夫です。
✔️食事のローテーションを試す
これは、毎日同じ食材、特に同じ種類のタンパク質ばかりを食べるのを避け、意識的に食材を循環させる方法です。
(例)月曜は鶏肉、火曜は魚、水曜は豚肉、木曜は卵や豆腐…
といった具合に、主菜を変えていきます。
こうすることで、特定の食材がお子さんの腸に与える負担を分散させ、炎症反応が起きるリスクを減らすことができます。
✔️「GFCF(グルテンフリー・カゼインフリー)」を試してみる
食事のローテーションでも改善が見られない場合、炎症の“火種”となりやすいグルテン(小麦)とカゼイン(乳製品)を、期間を決めて食事から抜いてみる方法が有効なことがあります。
(進め方の例)
1. 「まずは2週間」と期間を決める:
「一生やめる」と考えると大変ですが、「お試し期間」と考えると、ご家族の心理的な負担も軽くなります。
2. 簡単な置き換えから始める:
✔️牛乳 → 無調整豆乳、アーモンドミルク
✔️パン、麺類 → ご飯、米粉パン、米粉麺
✔️ヨーグルト → 豆乳ヨーグルト、甘酒
✔️小麦粉 → 米粉、片栗粉
3. 変化を観察する:
2週間後、お子さんのお腹の調子や便の状態、機嫌などに良い変化が見られるかを確認します。もし明らかな改善があれば、グルテンやカゼインが不調の一因であった可能性が高いと考えられます。
※GFCFは、自己判断で極端に行うと栄養が偏るリスクもあります。本格的に取り組む際は、ぜひ専門家にご相談ください。
ステップ3:消化力と腸内環境を育てる食材の選び方
刺激を減らすと同時に、腸を内側から強く育てていくための食材を積極的に取り入れましょう。これは、第2章で解説した「3つの柱」の総仕上げです。
【消化機能UP】のために、
✔️質の高いタンパク質:
卵、白身魚(たら、たい)、鶏肉(ささみ、胸肉)、豆腐など、消化しやすいものから。
✔️亜鉛:
赤身肉、レバー、牡蠣(カキフライなど)、納豆
✔️鉄:
赤身肉、レバー、あさり、小松菜(ビタミンCと一緒で吸収率UP)
✔️ビタミンB群:
豚肉、豆類、玄米(白米に混ぜるなど)
【腸内環境UP】のために
✔️プロバイオティクス:味噌、納豆、ぬか漬けなど日本の発酵食品。
✔️プレバイオティクス:わかめなどの海藻類、きのこ類、ごぼうなどの根菜類、玉ねぎ、バナナなど。
【炎症コントロール】のために
ビタミンD:鮭、さばなどの青魚、きのこ類。日光浴も大切です。
これらの食材を、先ほどお話しした「食事のローテーション」を意識しながら、日々の献立にバランス良く組み込んでいくことが、過敏な腸を根本から立て直すための王道と言えるでしょう。
▼今日から始めるアクションプラン
1. まずは1週間、簡単な食事記録をつける:お子さんの体の「声」を聴くことから始めましょう。
2. 主菜のローテーションを意識する:月曜は鶏肉、火曜は魚…というように、同じタンパク質が続かないように工夫してみましょう。
3. お味噌汁に海藻ときのこを入れる:腸内環境を育てる「プレバイオティクス」を手軽に摂取できます。
おわりに:ゴールは「快便」の先にある「快適な毎日」
ここまで、この記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。お子さんの繰り返す腹痛や便秘の背景にある「過敏な腸」という問題、そしてそのための3つの柱について、ご理解いただけたでしょうか。
私たちがこの記事を通してお伝えしたかった、最も大切なメッセージ。それは、治療のゴールは、単に「薬を使って便を出す」ことではない、ということです。
本当のゴールは、腸の過敏さそのものを取り除き、「またお腹が痛くなるかもしれない」というお子さんの日々の不安をなくし、心から安心して過ごせる「快適な毎日」をプレゼントしてあげることです。
お腹の調子が整うと、腸と繋がっている脳、つまりお子さんの心も落ち着きを取り戻します。朝、元気に「いってきます!」と家を出て、給食を楽しみ、お友達と心ゆくまで遊ぶ。そんな、当たり前のようでかけがえのない日常を取り戻すことこそ、私たちの目指す場所です。
もちろん、食事の工夫や生活習慣の改善は、根気のいる取り組みかもしれません。思うようにいかない日もあるでしょう。しかし、ご家族のその一つひとつの努力は、間違いなくお子さんの体の土台を築き、生涯にわたる健康という、何物にも代えがたい未来への投資となります。
どうか、ご家族だけで抱え込まないでください。
私たちは、その長く、しかし希望に満ちた道のりを、専門家として、そして一人の人間として、共に悩み、共に喜ぶ「伴走者」でありたいと心から願っています。
この記事が、見えない痛みに苦しむお子さんと、そのそばで寄り添うご家族にとって、一条の光となることを願ってやみません。
つらい便秘の根本原因を探り、お子さんの健やかな成長をサポートします。
「うちの子の場合はどうだろう?」「一度、専門的な視点で相談してみたい」
そう思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お子さんとご家族が、笑顔で毎日を過ごせるよう、私たちが全力でサポートします。
栄養に関する個別相談について
当院では、より専門的な栄養相談を個別で承っております。必要に応じて詳細な血液検査を行い、お子さん一人ひとりの栄養状態を客観的に評価した上で、最適な食事内容やサプリメントのご提案をいたします。
ご希望の方はお電話にて、「栄養相談希望」とお伝えください。
▶︎当院の分子栄養外来
この記事の執筆・監修者
小森こどもクリニック 院長 小森 広嗣(こもり こうじ)
慶應義塾大学医学部を卒業後、東京都立小児総合医療センターなどで小児外科医として豊富な臨床経験を積む。現在は地域のかかりつけ医として、日々多くのご家族と向き合っている。日本小児外科学会認定の小児外科専門医・指導医、医学博士。 「成長の感動や喜びをお子さん・ご家族と分か-ち合い、楽しく安心して子育てができる社会を創る」ことを自身のビジョンとし、診療や情報発信を行っている。
▶︎他におすすめの記事