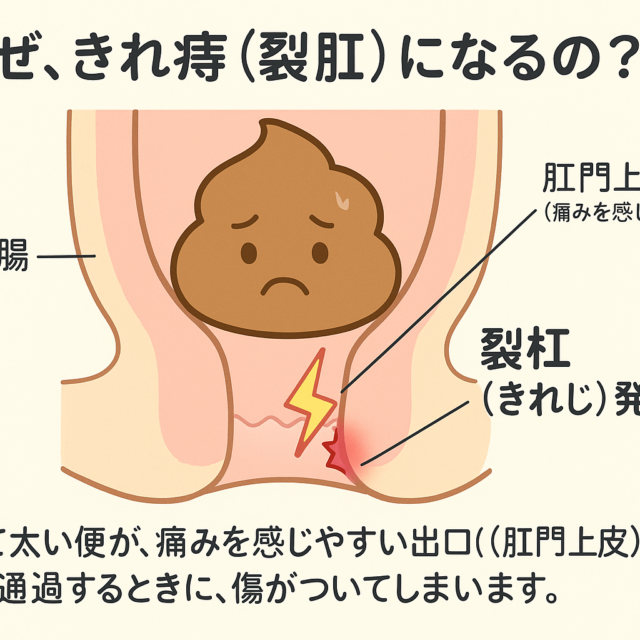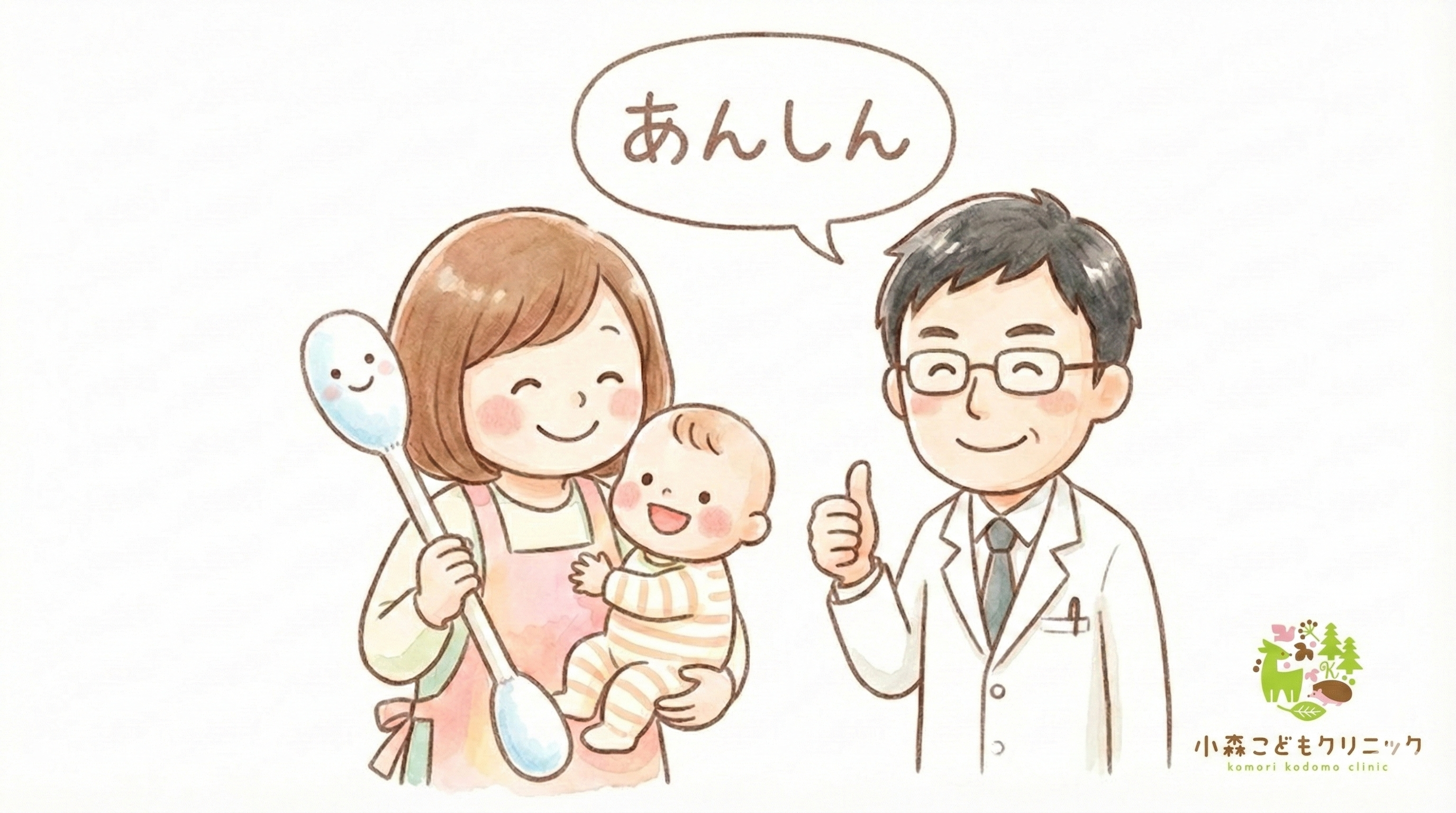目次
はじめに:お薬で少し楽になった今だからこそ、伝えたい食事の話

「毎日お薬を飲んでいるのに、まだスッキリしない日がある…」
「このお薬は、いつかやめられる日が来るのだろうか…」
クリニックの診察室で、私たちは日々、そうした保護者の皆様の切実な声に耳を傾けています。お子さんの便秘治療は、ご家庭にとって本当に根気のいる、長い道のりです。出口の見えないトンネルの中にいるように感じられることもあるかもしれません。
この記事は、そんな風に悩み、頑張っていらっしゃるご家族、お子さんのために書きました。
この記事のゴールは、便秘治療における食事の役割を正しく理解し、「100点満点を目指さない、でも着実にプラスになる」食事の工夫を、親子で楽しみながら見つけていただくことです。
先に一番大切なことをお伝えします。便秘治療の主役は、多くの場合「お薬」です。そして、食事は、そのお薬の効果を最大限に引き出し、便秘になりにくい“しなやかな腸”を育てるための、最高のサポーターです。
便秘治療は、ご家庭だけで抱え込むものではありません。私たちと、お子さん一人ひとりに合った、そしてご家族が無理なく続けられる治療法を、一緒に見つけていきましょう。
第1章:便秘治療の全体像と、私たちが目指すゴール
まず、私たちがどこを目指しているのか、そのゴールと道のりの地図を共有させてください。闇雲に進むのではなく、全体像を把握することで、ご家族の不安はきっと軽くなるはずです。
1-1. 私たちが目指すゴール:「3つのS」が達成された排便です
私たちが治療のゴールとして掲げているのは、シンプルに「3つのS」が達成された排便です。それは、お子さんにとって「排便が怖くない、気持ちの良い体験」になることを意味します。
① スッキリ(S)
便が残っている感じがなく、出し切った爽快感があること。
② すんなり(S)
強くいきまず、痛みもなく、短時間(5分以内)で自然に出せること。
③ しっかり(S)
育児書などではよく「バナナ状の便」が理想とされますが、私たちはそこにこだわりすぎる必要はないと考えています。お子さんの食べたものによって、便が少し硬くなる日も、柔らかくなる日もあって当然です。大切なのは「量」。お腹に溜まっていた分がしっかりと出て、お腹がスッキリしている状態であれば、それがその子にとっての良い排便と言えるでしょう。
「毎日出ているか」という回数だけにとらわれるのではなく、この「質」と「量」を大切に考えています。
1-2. ゴール達成のための「治療の三本柱」
この「3つのS」というゴールを達成するために、私たちは3つの治療法を柱として、柔軟に組み合わせていきます。
柱① 内服薬(飲み薬)
便を柔らかく保ち、排便しやすくするための治療の「土台」です。国際的にはマクロゴール(商品名:モビコール®︎)が推奨されていますが、味が苦手だったり、量が飲めなかったりするお子さんもいます。大切なのは、お子さんが毎日無理なく「続けられる」こと。酸化マグネシウムやラキソベロン®︎、時には漢方薬なども含め、ご家庭の状況を伺いながら、その子にとって最適な処方を一緒に見つけていきます。
柱② 浣腸・坐薬
排便のリズムを整えるための頼れる「サポーター」です。お薬を飲んで便が柔らかくなっても、出すことへの恐怖心から溜めてしまうお子さんは少なくありません。そんな時、浣腸は「痛みなくスッキリ出せた!」という成功体験をさせてあげられる、重要なリセットボタンになります。これは決して治療の失敗ではなく、ゴールへの近道となる積極的な一手なのです。
柱③ 食事・生活習慣
便秘になりにくい丈夫な腸を育てるための「土壌づくり」です。お薬の効果をしっかり高め、将来的にお薬からの卒業を目指すための、最も根本的で、息の長いアプローチと言えるでしょう。この記事では、この3本目の柱について、詳しくお話ししていきます。
1-3. お子さん一人ひとりにあわせた「オーダーメイド治療」を
この3つの柱を、ご家族の思い(悩み、目標、ゴール)やお子さんの日々の様子を丁寧に見ながら、どう組み合わせていくか。それこそが、私たちが最も大切にしている「オーダーメイドの便秘治療」です。誰一人として、全く同じ治療法になることはありません。
第2章:「腸内環境」を整えるとは? お腹の中で起きている3つの大切なこと
さて、ここからは3本目の柱である「食事」の話です。「腸内環境を整えましょう」とよく言われますが、それは一体どういうことなのでしょうか。
2-1.【比喩で解説】良い腸内環境は、まるで「豊かな畑」
お子さんの腸の中を、一つの「畑」として想像してみてください。この畑で、毎日美味しい野菜(=理想的な便)が育つためには、3つの大切な要素が必要です。
① 栄養満点の「土壌」(多様な腸内細菌)
② 畑を耕す「力」(健やかな腸の動き)
③ 水や栄養を保つ丈夫な「畝(うね)」(健康な腸の粘膜)
これら3つが互いに支え合うことで、初めて理想的な排便が生まれます。食事療法は、この3つすべてに働きかけることを目指します。
2-2. 要素① 豊かな土壌(腸内細菌のバランス)
お子さんのお腹の中には、たくさんの種類の腸内細菌、いわゆる「善玉菌」たちが住んでいます。彼らは、食事として摂り入れた食物繊維をエサにして、私たちの体にとって非常に有益な『短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)』というスーパー物質を作り出してくれます。
この『短鎖脂肪酸』こそが、腸内環境全体の“司令塔”です。後述する「腸の動き」の直接的なエネルギー源となり、「腸の粘膜」を健康に保つための栄養にもなる、まさに縁の下の力持ちなのです。
2-3. 要素② 畑を耕す力(腸のぜん動運動)
腸は、便を肛門まで運び出すために、それ自体がイモムシのように、リズミカルに動いています。これを「ぜん動運動」と呼びます。この畑を耕す力には、2つのものが必要です。
1. エネルギー:ぜん動運動を動かすためのガソリン。これが、先ほどの『短鎖脂肪酸』です。
2. 適度な刺激:便そのものがある程度の“かさ”を持つことで、腸の壁が内側から優しく刺激され、「動け!」というスイッチが入ります。
便秘が続いて便が溜まると、腸が伸びきってしまい、この動き自体が鈍ってしまうという悪循環に陥ります。
2-4. 要素③ 丈夫な畝(腸の粘膜バリア)
腸の表面は、絨毯のようにびっしりと粘膜で覆われています。この粘膜は、食べ物から必要な栄養だけを吸収し、体にとって不要なものをブロックするという、非常に大切な「関所」の役割を担っています。
この粘膜が健康であることは、腸全体のコンディションを良好に保ち、スムーズな排便の土台となります。
2-5. 食事療法が目指すもの
これからお話しする食事療法は、決して魔法ではありません。
食物繊維を摂ることで、畑の「土壌」を豊かにし(腸内細菌↑、短鎖脂肪酸↑)。
その結果、畑を耕す「力」を力強くし(ぜん動運動↑)。
そして、畑の「畝」を丈夫にする(粘膜の健康↑)。
このように、お子さんの腸が本来持っている力を、根本から、そして穏やかに引き出してあげることを目的としているのです。
第3章:【ステップ1:はじめの一歩編】いつもの食事に「ほんの少し」をプラスする習慣
さて、ここからはいよいよ実践編です。
ですが、どうか身構えないでください。特別な料理を作る必要も、食生活をガラリと変える必要もありません。
3-1. 目指すは「完璧な献立」ではなく「昨日よりプラスワン」
私たちがご家庭にお願いしたいのは、たった一つ。「いつもの食事に、何か一つだけ、腸が喜ぶものをプラスしてみる」という小さな習慣です。
完璧な便秘解消メニューを目指す必要はありません。好き嫌いのあるお子さんに、無理に食べさせる必要もありません。今日の食卓に、何か一つでもプラスできたら、それはもう120点満点です。その小さな一歩が、お子さんの「豊かな畑」を育てる、何よりの力になります。
3-2. 主食にプラスワン:白米に「もち麦」を混ぜてみる
まず最も簡単で、効果を実感しやすいのが主食の工夫です。
いつもの白米を炊くときに、もち麦や押し麦を、まずはスプーン1杯から混ぜて炊いてみてください。これだけで、腸内細菌たちのごはん(水溶性食物繊維)がぐっと増え、畑の『土壌』を豊かにする確実な第一歩になります。お子さんの様子を見ながら、少しずつ割合を増やせると良いでしょう。
パンが好きなお子さんなら、週に1〜2回、いつもの食パンを全粒粉パンやライ麦パンに変えてみるのも素晴らしい工夫です。
3-3. 汁物にプラスワン:お味噌汁の具を増やしてみる
次におすすめなのが、お味噌汁やスープです。
いつものお味噌汁やスープを作るときに、乾燥わかめを少し足す。あるいは、なめこや細かく刻んだオクラを加えてみる。たったこれだけです。
こうしたネバネバした食材に含まれる水溶性食物繊維は、腸の粘膜を優しく保護し、畑の『畝(うね)』を丈夫にするのをサポートしてくれます。
3-4. おやつをチェンジ:スナックを果物に変えてみる
おやつの時間は、お子さんの腸を応援する絶好のチャンスです。
いつも食べているスナック菓子やチョコレートを、週の半分だけでも、バナナやキウイフルーツ、りんご、梨といった季節の果物に変えてみてください。
また、干し芋や、ふかしたサツモイモ(焼き芋)も、食物繊維と自然な甘みが摂れる最高のおやつと言えるでしょう。
果物やいも類は、腸内細菌のエサになるだけでなく、便の材料となり、腸を動かす『力』そのものを応援してくれます。
どうでしょうか。
「これなら、何か一つでも始められそうな気がする」と思っていただけたら、これ以上嬉しいことはありません。
まずはこの『プラスワン』の習慣に、ご家族で無理なく慣れることが何よりの第一歩です。そして、もし「もう少し頑張れそう」と思えたら、次のステップに進んでみましょう。
第4章:【ステップ2:慣れてきたら編】腸がもっと喜ぶ!食材バラエティ戦略
「プラスワン」の習慣に少し慣れてきたら、あるいは「もう少し何かできそう」と感じたら、次はお子さんの腸をさらに応援するための、食材選びの“ちょっとしたコツ”をご紹介します。
これもまた、完璧にこなす必要は全くありません。知識として知っておくだけで、スーパーでの食材選びが少し楽しくなるかもしれません。そんな気軽な気持ちで読み進めてください。
4-1. 2種類の食物繊維で、「土壌」と「耕す力」の両方を応援する
食物繊維には、大きく分けて2つのタイプがあることをご存知ですか?それは「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」です。
あの「豊かな畑」の比喩で言うなら、それぞれが違う大切な役割を担っています。
✔️水溶性食物繊維:豊かな『土壌』のメインディッシュ
【役割】
水に溶けてゲル状になり、便を柔らかく、そして“ツルン”と滑りやすくしてくれます。何より、腸内細菌たちの大好物であり、『短鎖脂肪酸』を作り出すための最高のエサになります。まさに、畑の土壌を豊かにしてくれる栄養そのものです。
【多く含まれる食材】
もち麦・押し麦、オートミール、海藻類(わかめ・昆布)、果物、オクラ、長いもなど。
✔️不溶性食物繊維:畑を耕す『力』のサポーター
【役割】
水に溶けにくく、便の“かさ”を増やしてくれます。その結果、腸の壁が優しく刺激され、「便を押し出そう!」というぜん動運動のスイッチを押す手助けをしてくれます。畑を耕す力を物理的にサポートしてくれる存在です。
【多く含まれる食材】
きのこ類、豆類、根菜類(ごぼう・にんじん)、玄米、さつまいもなど。
外来でよく「どちらを意識すれば良いですか?」と聞かれますが、まず私たちがおすすめしているのは、腸内細菌のエサとなる「水溶性食物繊維」を優先的に意識することです。不溶性食物繊維も大切ですが、摂りすぎると逆にお腹が張ってしまうことがあるため、まずは土壌を豊かにすることから始めるのが、最も穏やかで効果的なアプローチだと考えています。
4-2. 便秘改善の“特効薬”となりうる2つの成分
さらに、食材の中には、便秘改善の頼もしい味方となる特別な成分を持つものがあります。
✔️天然の緩下剤「ソルビトール」
これは、プルーンや西洋なし、りんごなどに特に多く含まれる天然の糖アルコールの一種です。腸の中で水分をぐっと引き寄せる働きがあり、便を柔らかくしてくれます。お薬に頼りたくない日の“お守り”として、プルーンジュースを少し飲んでみる、といった活用も良いでしょう。
✔️腸内細菌の特別なごはん「レジスタントスターチ」
これは「難消化性でんぷん」とも呼ばれ、食物繊維と似た働きをします。特に、腸の奥に住む腸内細菌まで届く、特別なごはんだと考えてください。面白いことに、このレジスタントスターチは、炊いたご飯やじゃがいもが“冷める”過程で増える性質があります。おにぎりやポテトサラダは、実は腸活メニューでもあるのです。
4-3. 1日のモデル献立(体をつくる栄養素も意識した一例です)
これまでの知識を詰め込んだ、とある一日の献立例です。 でも、どうか「この通りにしなきゃ!」とは思わないでくださいね。
これは、あくまでたくさんの引き出しの一つです。ご家庭の食卓に気軽に取り入れられそうなヒントを、何か一つでも見つけていただくための、アイデア集のようなものだと考えていただけると嬉しいです。
食物繊維はもちろん大切ですが、ここで忘れてはならない視点が一つあります。それは、腸も体の一部であり、健康な体があって初めて腸も元気に働くということです。
体を作るタンパク質、エネルギー源となる質の良い炭水化物、そして体の調子を整えるビタミンやミネラル(特に不足しがちな鉄分)。これらが揃ってこそ、食物繊維もその力を最大限に発揮できます。
「こんな風に組み合わせると、腸だけでなく体全体が喜ぶのか」というヒントとして、眺めてみてください。
✔️朝ごはん
きな粉とすりゴマを入れたオートミール。牛乳や豆乳で煮て、季節のベリーを添える。
(ポイント)
きな粉やゴマは、手軽にタンパク質と鉄分、カルシウムを補給できる素晴らしい食材です。ベリー類に含まれるビタミンCは、植物性の鉄分の吸収を高めてくれます。
✔️昼ごはん
鮭フレークと刻みひじきを混ぜ込んだ、もち麦ごはんのおにぎり。豚汁(豆腐、根菜、豚肉入り)。
(ポイント)
鮭や豚肉、豆腐で、体の材料となるタンパク質をしっかりと。ひじきは鉄分やミネラルの宝庫です。具沢山の汁物は、野菜とタンパク質を一度に摂れるため、好き嫌いのあるお子さんにもおすすめです。
✔️おやつ
ふかし芋、または季節の果物。無調整豆乳や少量のチーズを添えて。
(ポイント)
おやつにも少量のタンパク質(豆乳、チーズ)を組み合わせることで、満足感が持続しやすくなります。ふかし芋は、エネルギー源となる良質な炭水化物と食物繊維の優れた供給源です。
✔️夜ごはん
鶏ひき肉とレンズ豆、刻んだパプリカやほうれん草をたっぷり入れたドライカレー。麦ごはんと、わかめとキュウリの和え物を添えて。
(ポイント)
鶏ひき肉でタンパク質と鉄分を確保しつつ、レンズ豆で食物繊維をさらに強化。色の濃い野菜(パプリカ、ほうれん草)を加えることで、腸の粘膜を強くするのに役立つビタミンAなどの栄養素も補給できます。
繰り返しになりますが、これはあくまで理想形の一つです。この中から一つでもご家庭の食卓に取り入れられそうなヒントがあれば、それが何よりの大きな一歩です。
第5章:保護者の皆様の「これ、どうなの?」に答えるQ&Aコーナー
ここでは、日々の診療で保護者の皆様からよくいただくご質問にお答えします。きっと、あなたが今まさに抱えている疑問や不安も、この中にあるはずです。
Q. うちの子、マクロゴール(モビコール®︎)がどうしても飲めないのですが、他のお薬はありますか?
A. もちろんです。そして、これは私たちのチームが治療において非常に大切に考えている点です。
確かにマクロゴールは、国際的にも推奨されている安全で有効なお薬ですし、現在多くの小児科クリニックで第一選択薬のような位置づけになっています。
しかし、私たちは「良い薬」イコール「その子にとってベストな薬」とは限らないと考えています。
便秘治療は、数ヶ月、時には年単位で続く長い道のりです。その治療の成否を分ける最大の鍵は、「ご家庭が無理なく、そして毎日きちんと継続できること」に尽きます。
「ジュースに混ぜないと飲んでくれない」「お水ではどうしても嫌がる」…そうした状況で毎日お薬を準備するのは、ご家族にとって大きな負担になりますし、糖分の摂りすぎも気になります。それでは、どんなに優れた薬であっても、その子にとってのベストな治療とは言えないでしょう。
私たちのチームが何よりも大事にしているのは、薬のブランドや新しさではありません。昔から使われている酸化マグネシウムやピコスルファートナトリウム(ラキソベロン®︎)なども含め、その子にとって第1章でお話しした「3つのS(スッキリ、すんなり、しっかり)」が無理なく維持できるかどうか、ただその一点です。
ですから、一つの薬にこだわりすぎる必要は全くありません。お子さんの好みやご家庭の生活スタイルに合わせて、様々な選択肢の中から、その子だけの「ベストな処方」を一緒に探していくことこそが、私たちの役割だと考えています。どうぞ、遠慮なく「このお薬は飲みにくいです」と私たちに伝えてください。
Q. 浣腸を使うことに抵抗があります。癖になったりしませんか?
A. そのご心配、非常によく分かります。「癖になるのでは?」という不安は、多くの保護者の方がお持ちです。
結論から申し上げますと、医師の指示のもとで適切に浣腸を使う分には、癖になることはまずありませんのでご安心ください。
便秘治療における浣腸の役割は、毎日使い続けることではなく、「溜まってしまった便を一度リセットし、悪循環を断ち切る」ことです。
硬い便で一度でも痛い思いをすると、お子さんは排便そのものに恐怖心を抱き、無意識に便を我慢するようになります。これが「痛み→我慢→さらに便が硬くなる→さらに痛い」という最悪のスパイラルです。浣腸は、このスパイラルを断ち切るための「重要なリセットボタン」なのです。「痛くなく、スッキリ出せた!」という成功体験は、お子さんの排便への恐怖心を和らげるための、何よりの薬になります。
Q. 食物繊維を増やしたら、逆にお腹が張って苦しそうです。なぜですか?
A. これは、良かれと思って食事を工夫した際に、しばしば起こることです。原因は主に2つ考えられます。
1. 急に増やしすぎた
腸内細菌たちも、急な食事の変化に驚いてしまいます。慣れない食物繊維が一度にたくさん入ってくると、腸内細菌がそれを分解する過程でガスがたくさん発生し、お腹が張ってしまうのです。
2. 不溶性食物繊維が多かった
きのこや根菜に多い不溶性食物繊維は、便のかさを増す働きがありますが、水分が足りなかったり、腸の動きがまだ鈍かったりすると、かさが増した分だけお腹の張りにつながることがあります。
対策は、「ゆっくり、少しずつ」です。まずはお味噌汁にわかめを少し足す、といった本当に小さなステップから始め、お子さんのお腹の様子を見ながら、1〜2週間かけて慣らしていくのが良いでしょう。まずは水溶性食物繊維(もち麦、海藻、果物など)から意識してみるのがおすすめです。
Q. 好き嫌いが激しい子には、どうやって食物繊維を摂らせれば良いですか?
A. 好き嫌いへの対応は、本当に根気がいりますよね。お気持ち、痛いほど分かります。
ここでのコツは、「食べさせる」と意気込むのではなく、「気づかれないように、ほんの少し混ぜ込む」という作戦です。
✔️スープやカレー、ミートソースに溶け込ませる
玉ねぎやにんじん、きのこなどを細かく刻んで、じっくり煮込んでしまえば、多くの場合は気づかずに食べてくれます。レンズ豆は煮込むと形がなくなるので、特におすすめです。
✔️ハンバーグやつくねに混ぜ込む
刻んだきのこやひじき、おからなどを少量混ぜ込んでも、味はほとんど変わりません。
✔️ホットケーキやお好み焼きに入れる
きな粉や細かく砕いたオートミール、すりおろした野菜などを生地に少し混ぜてみましょう。
大切なのは、食事の時間が親子にとって苦痛な時間にならないことです。一口でも食べられたらたくさん褒めてあげる。たとえ食べてくれなくても、食卓に出し続ける。その根気強い繰り返しが、いつかきっと力になります。
Q. 牛乳や乳製品は、便秘には良くないと聞きましたが本当ですか?
A. これは、非常に専門的な判断が必要になる、大切なご質問です。
まず最も重要なこととして、ほとんどのお子さんの便秘は、牛乳や乳製品とは無関係です。*これらは成長に欠かせない優れた食品ですので、ご自身の判断で食卓から除くことは絶対に避けてください。
ただし、『お薬をしっかり使い、食事の工夫をしても、どうしても改善しない』という一部の難治性のお子さんの中に、牛乳に含まれるタンパク質が影響しているケースがあることが、専門家の間では知られています。
これは、じんましんが出るような、一般的にイメージされるアレルギー反応とは全く異なります。
一部のお子さんでは、その子自身の体質と牛乳のタンパク質との間に「相性」のようなものがあり、そのタンパク質が腸の粘膜、特に便の出口に近い部分で、ごく軽微な炎症反応を持続的に起こしてしまうことがあるのです。
これは、派手な火事とは全く違い、例えるなら“くすぶり続ける小さな火種(ボヤ)”のような状態です。この“火種”があると、お子さんは排便のたびにチリチリとした痛みや不快感を覚えるようになります。その不快感から、無意識のうちに排便を我慢するようになり、結果として便が硬くなり、さらに強い痛みを感じる…という悪循環に陥ってしまうのです。
もし、この可能性が考えられる場合は、必ず私たち医師の監督のもとで、期間を決めて牛乳・乳製品を食生活から完全に除く『除去試験』を行います。これは、原因を探るための『診断的な治療』です。
繰り返しますが、これは専門的な判断を要します。決してご家庭の判断では行わず、まずはかかりつけの医師に『いろいろ試しても便秘が良くならないのですが…』と、相談してください。
第6章:食事の効果を最大限に引き出す、毎日の“ちょこっと”習慣
食事の工夫と合わせて、ほんの少しだけ生活習慣を見直すことで、腸はさらにスムーズに動き始めます。これもまた、「できたらラッキー」くらいの気軽な気持ちで試してみてください。
6-1. 体が持つ最高の排便リズム「胃・結腸反射」を味方につける
私たちの体には、食後に自然と便意が起きやすくなる、素晴らしい仕組みが備わっています。それが「胃・結腸(いけっちょう)反射」です。
これは、食べ物が胃に入って胃が膨らむと、その信号が大腸に伝わり、「新しい食べ物が入ってきたから、古いものを送り出す準備をしよう!」と、ぜん動運動が活発になる現象です。この排便の“ゴールデンタイム”を、ぜひ習慣にしてみましょう。
✔️朝食の後が、特におすすめです。
食後15〜30分以内を目安に、「トイレに行ってみる?」と優しく声をかけ、便座に3〜5分ほど座る習慣をつけてみましょう。
排便の時に何よりも大切なのは、お子さんが「ここでなら安心して出せる」と感じられる環境です。
お子さんには、一人ひとり、その子なりの「いきみやすいスタイル」があります。便座に座って足を浮かしたまま上手にいきめる子もいれば、便座の上でカエルのようにしゃがみこむスタイルが好きな子もいます。お父さんやお母さんがそばにいてくれるだけで、安心して出せる子もいるでしょう。
もし、お子さんが足がぶらぶらして不安定そうにしていたり、どこか不安そうにしていたりするなら、試してみてほしい工夫の一つが足台(ステップ)です。
足がしっかりつくことで体が安定し、安心感につながる場合があります。また、結果的にひざが上がる姿勢になることで、医学的に見ても直腸がまっすぐになり、スムーズないきみの助けになることも知られています。
ですが、これも絶対ではありません。足台があった方がスムーズな子もいれば、なくても全く問題ない子も大勢います。一番大切なのは、ご家庭で色々と試してみて、その子に合った「安心スタイル」を見つけてあげることだと、私たちは考えています。
出なくても全く問題ありません。「座れただけでエライね!」と褒めてあげてください。絵本を読んだり、歌を歌ったり、トイレを楽しい場所にすることが、何よりの秘訣です。
6-2. 腸への心地よい刺激となる「適度な運動」
「便秘には運動を」と言われると、なんだか大変そうに聞こえるかもしれません。ですが、お子さんに腹筋やランニングをさせる必要は全くありません。
私たちが考える最高の運動は、シンプルに「外で元気に、楽しく遊ぶ」ことです。
公園で走り回る、ジャンプする、ダンスを踊る。そうした全身運動は、自然とお腹周りの筋肉を使い、腸に心地よい刺激を与えて、ぜん動運動を活発にしてくれます。
特別な運動は何もいりません。お子さんが笑顔でいられる時間を、少しでも長く作ってあげること。それが、腸にとっても一番の薬になるのです。
おわりに:食事療法は「点数」で評価するものではありません
ここまで、本当に長い文章を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
たくさんの情報をお伝えしましたが、どうか「あれもこれも、全部やらなければ」と気負わないでください。この記事でお伝えした食事療法は、決して「点数」で評価するものではありません。
「今日は、お味噌汁にわかめを足せた」
「おやつのポテトチップスを、バナナに変えられた」
その一つひとつの小さな選択が、目には見えなくても、お子さんの腸の「豊かな畑」を確実に育んでいます。
そして最後に、私たちが便秘の治療を含め、すべての子育てにおいて最も大切にしている価値観をお伝えさせてください。
それは、物事を「正しいか、間違いか」で裁いたり、「できたか、できなかったか」という結果だけで一喜憂憂したりするのではなく、常に“より良い方向”を目指して工夫し続けるプロセスそのものを大切にする、という考え方です。
子育てに、絶対的な「正解」はありません。昨日うまくいった方法が、今日はうまくいかないかもしれない。インターネットで見つけた「正しい」情報が、必ずしも目の前のお子さんに合うとは限らない。それでいいのです。
大切なのは、うまくいかない時にご自身やお子さんを責めるのではなく、「じゃあ、次はこうしてみようかな?」と、ほんの少しだけ視点を変えてみること。その試行錯誤のプロセスこそが、ご家族を、そしてお子さんを成長させてくれる何よりの力になると、私たちは信じています。
完璧を目指さず、昨日より半歩でも前に進めたら、それで十分。一段、また一段と、お子さんと一緒に階段を登っていく。その歩み自体を、私たちは全力で応援したいのです。
便秘治療の道のりは、長く、根気がいるものですが、決してご家族だけで歩むものではありません。
私たちクリニックは、いつでもご家族の「伴走者」です。困ったとき、迷ったときは、どうぞお気軽に「先生、ちょっと聞いてもらえますか?」と声をかけてください。一緒に悩み、一緒に考え、お子さんの健やかな毎日への道を、伴に走らせていただければ幸いです。
この記事の執筆・監修者
小森こどもクリニック 院長 小森 広嗣(こもり こうじ)
慶應義塾大学医学部を卒業後、東京都立小児総合医療センターなどで小児外科医として豊富な臨床経験を積む。現在は地域のかかりつけ医として、日々多くのご家族と向き合っている。日本小児外科学会認定の小児外科専門医・指導医、医学博士。 「成長の感動や喜びをお子さん・ご家族と分か-ち合い、楽しく安心して子育てができる社会を創る」ことを自身のビジョンとし、診療や情報発信を行っている。
当院の便秘外来を受診希望の方は
こちらよりご予約ください